人は知性を持ち、善悪を判断し、理性的に考える力を与えられている。
私たちは「何をすべきか」「どちらが正しいか」を、ある程度知っている。
たとえば──
・早寝早起きが健康に良いこと
・感謝を言葉にすることが人間関係を良くすること
・目標を持ち、計画的に努力することが未来を変えること
これらは、考えるまでもなく“正しい”。
だが同時に、それらを実行できる人間は少ない。
この奇妙な矛盾は、いったいどこからくるのだろうか。
「認識」と「実行」の間にある、見えない断絶
古代ギリシャの哲学者ソクラテスは、
「人は善を知れば、それを行う」と考えた。
つまり“知ること”こそが、人間にとって行動の原動力であると。
しかし現代に生きる我々は、それを疑わざるを得ない。
私たちは多くのことを「知って」いるが、
しばしば「行わない」からだ。
これはもはや単なる怠惰ではない。
むしろ、人間とは本質的に、行動と認識の間に裂け目を持った存在なのではないか。
意志という名の「橋」
この裂け目を渡るには、「意志」という橋が必要だ。
だが意志は、極めて壊れやすく、あいまいで、風に吹かれれば折れてしまう細い木の橋のようだ。
・やるべきことが分かっていても、気分が乗らない
・正しい選択が見えていても、恐れが先に立つ
・誰かのために動きたいと思っても、自分を優先してしまう
こうした“微かな感情の風”が、橋をぐらつかせる。
人は合理的であると同時に、情動に支配された存在でもある──
この両義性こそが、私たちの「分かっているのにやらない」という現象を生み出している。
では、どうすれば人は「実行する」人になれるのか
それはおそらく、“行為そのものに意味を見る”ことから始まる。
「これをやれば◯◯になるから」ではなく、
「これをすることが、私自身であるから」と捉え直す。
掃除をするのは、部屋をきれいにするためではなく、
「整った空間にいる自分」でいたいから。
早く寝るのは、健康になるためではなく、
「自分を大切にしたい」という意志の現れとして。
そこに“自己との一致”が生まれたとき、
ようやく「知っている」が「やっている」に変わる。
結びに──人間は、完成しない存在である
私たちは、常に理想と現実の狭間で揺れている。
分かっていてもできない自分を責めることもある。
だが、それこそが人間であり、
その不完全さの中にこそ、「なりたい自分」への希求が宿るのではないか。
哲学とは「生き方を考えること」だと、かつて誰かが言った。
ならば今日、ほんの少しでも“分かってることをやってみよう”とするその意志こそが、私たちを哲学的な生へと導いているのかもしれない。
この文章もまた、
「書いたほうがいい」と思いながら、やらずにいた私の「分かってたけどやってなかったこと」だったのかもしれません。読んでくれて、ありがとう。


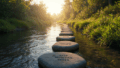
コメント