本記事を見ていただきありがとうございます。
うつ病・適応障害で働けなくなったとき、何よりも不安なのは「収入がなくなること」ではないでしょうか。そんなときに頼れる制度のひとつが、傷病手当金です。
将来のお金の不安で辞めるのを躊躇っている方、会社に迷惑かもと思っている方、自分の体調を第一に考えて辞める勇気を出しましょう。ここで紹介する傷病手当金が力になるはずです。
この記事では、
- 傷病手当金の基本ポイント
- 実際の手続きで苦労したこと
- これを知っておくと安心できるポイント
- 我が家の体験談
を、できるだけわかりやすくまとめています。
同じように悩んでいる方に、少しでも力になれたら嬉しいです。
■ 傷病手当金ってどんな制度?
ざっくり言うと、
「病気やケガで働けなくなったときに、収入の約2/3を補ってくれる制度」
です。
健康保険(社会保険)に加入している人が使える制度で、
精神疾患(うつ病・適応障害・不安障害など)も対象になります。
支給期間は最大 1年6ヶ月。
さらに失業保険も加えると最大2年6ヶ月支給を貰いながら休養できます。
精神疾患の場合は、回復に時間がかかることも多いので、
この2年半の支援は本当に大きな助けになります。
■ 我が家が「傷病手当金」を知ったタイミング
夫の体調が悪くなり、会社に行けなくなった頃、
私たちはまだこの制度のことを正しく理解していませんでした。
「休んだら給料がゼロになっちゃうの…?」
「会社を辞めたらどうなるの?」
と不安だらけで、夜は寝つきも悪かったほど。
そんなとき、ネット検索でたまたま「退職後も受け取れる」という情報を見つけ、
そこから制度について必死で調べました。
結果として、我が家は 退職後も傷病手当金を受給 することができました。
もしこの制度を知らなかったら、
生活費は完全に不足していたはずで、
夫の回復にも悪影響が出ていたと思います。
■ 受給が始まって感じたこと
率直な感想は、
「本当に……助かった」
この一言に尽きます。
生活費のすべてを補うわけではありませんが、
家賃や食費など、最低限の生活の基盤を支えてくれました。
そして何より大きかったのは、
「収入ゼロではない」という精神的な安心感。
収入の不安が少し軽くなることで、
夫が回復に向き合う余裕も生まれました。
制度の存在を知って、申請して、本当に良かったと感じています。
■ 傷病手当金を受け取りたい方へ
☑“早め”に動いてほしい
退職してからだと受け取れない可能性があります。
退職前から傷病手当金受給に向けて準備しましょう。
☑ 医師に現状を正直に伝えてほしい
「まだ働けるかも…」と無理をしてしまいがちですが、
医師は正しい診断をするために、ありのままを知る必要があります。
☑ 社会保険の窓口に遠慮なく相談していい
窓口の方は丁寧に教えてくれます。
不安なときは電話でもOKです。
☑ 「退職後も受給できる」ことを忘れないで
働けないまま退職してしまう人は多いです。
そんなときこそ制度が力になります。
■ 我が家からのメッセージ
うつ病は「目に見えない病気」だからこそ、
他の誰にも気づかれず、
ひとりで抱え込んでしまうことが多いと思います。
でも、働けないのはあなたのせいではありません。
必要なのは「休むこと」と「助けを借りること」。
傷病手当金は、その“助け”の一つです。
もし今つらさの中にいる方がいたら、
どうかひとりで悩まずに、
制度を頼ってほしいと思います。
これから、我が家の経験や傷病手当受給までの流れについて発信していきますので、
他の記事も是非確認してください。我が家の経験が、その一助になれば嬉しいです。

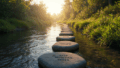

コメント